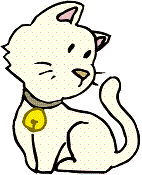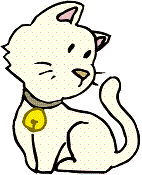2008年 本波 隆(ほんなみ たかし)福祉関係ニュース
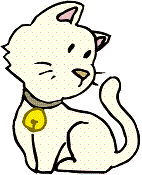
2008年(平成20年)6月13日(金)北日本新聞 富山県版
お年寄りに映画”出前”
社協宇奈月 旧黒部で初開催
黒部市社会福祉協議会宇奈月支所(旧宇奈月町社会福祉協議会、本波隆支所長)の出前映画会「来て見てヤンバイ映画館」が十二日、初めて旧黒部市地域で開かれた。会場となった黒部市生地中区の生地コミュニティーセンターには約六十人のお年寄りが訪れ、藤山寛美らが出演した人気映画を楽しんだ。
出前映画会は家に閉じこもりがちな高齢者が外出する機会を増やそうと、旧宇奈月町社会福祉協議会が平成十三年かに始めた。
「ヤンバイ」は県東部の方言で「良かった」という意味。月二回、宇奈月地域の公民館などで「男はつらいよ」「釣りバカ日誌」などを上映してきた。旧黒部市区域でも上映を希望する声が多く、今回初めて開催した。
この日は藤山寛美や渋谷天外らが出演する喜劇「親バカ子バカ」など三本を上映した会場は、藤山寛美がこっけいな演技を見せるたびににぎやかな笑い声に包まれた。
次回は七月三十日に黒部市の石田公民館で開く。
カラー写真(省略)
人気映画の上映を楽しむお年寄り
2008年(平成20年)6月12日(木)日本経済新聞 全国版 夕刊
うたた寝
来て、見て、良かった月2回
黒部峡谷の入り口にあたる富山県黒部市宇奈月町で毎月二回、巡回映画会が開かれるようになって七年たつ。上映されるのは「愛染かつら」「君の名は」「鐘の鳴る丘」といった懐かしい作品。見に来たお年寄りが「ヤンバイ(良かった)ヤンバイ」と喜ぶことから「来て見てヤンバイ映画館」と呼ばれている。
発案したのは宇奈月町社会福祉協議会(現在は黒部市社会福祉協議会宇奈月支所)の本波隆さん(57)。人口約六千人の宇奈月町では高齢者が三割を占め、家に閉じこもりがちな人も増えている。「元気で長生きしてもらうには外出の機会を」と考えた本波さんは、子供のころ楽しみだった巡回映画を思いついた。
地元高校を卒業後、二十年近くを東京で生活していたこともあって、「地方の高齢者には娯楽が少なすぎる」との思いもあった。
会場となるのは町内七カ所の公民館。本波さんは事前にその地区の全戸に安否確認を兼ねてチラシを配って歩く。そして当日、三々五々集まってくるお年寄りたちを懐メロで迎える。全員が席に着いたら軽い体操の後、上映。映画が終わってもおしゃべりに興じている人がいれば、話が尽きるまで辛抱強くつき合う。
これまで開催したのは百六十七回。その地区の家の葬儀と重なって観客がゼロだったこともある。反対に「続・男はつらいよ」を上映した時には、地区の在宅のお年寄りほぼ全員、七十人が集まった。
当初、手持ちの映画ビデオは四十本ほどだったが、寄贈を受けて今では四百本以上に。一人でも多くのお年寄りから「ヤンバイ」の声が聞きたいと、本波さんの”次回上映作”選びには一段と熱が入っている。
(編集委員 深堀純)
2008年(平成20年)5月26日(月)北陸中日新聞 富山県版
ウチの押し
市社協宇奈月支所の懐メロライブラリー
善意を生かし上映会
整理棚をぎっしりと埋めるレコード盤。片方の棚には映画のビデオやDVDがずらり。廊下には貴重な16ミリフィルムが積まれてある。
すべてが寄贈品だ。ここは黒部市宇奈月町社会福祉協議会宇奈月支所。「データベース化に大忙しですよ。でも、きちんと分類しないと、宝の持ち腐れになれいますから」と、本波隆支所長(57 )は話す。
レコード約一万枚、ビデオ・DVDは四百三十七本、16ミリフィルムは二百八十三巻に及ぶ。収集のきっかけは十一年前、ある視覚障害者が漏らしたひと言だった。
「懐メロが聴きたい」−。視覚障害者にとって音楽は貴重な娯楽。要望に応えたいとテレビなどで音楽作品の提供を募ったところ、三重県の男性から届いた百枚を皮切りに、レコードはどんどん増えていった。
家に閉じこもりがちな高齢者には映画を楽しんでもらおうと、独自の映写会を企画。こちらも活動が知れ渡るにつれ、ビデオやDVDが贈られてくるようになった。本波支所長は「善意を無駄にせず、大切に活用していきたいです」と感謝している。
(平井剛)
カラー写真(省略)
県内外から寄贈された貴重なレコード盤や16ミリ映画フィルム=黒部市宇奈月町浦山で
2008年(平成20年)4月19日(土)朝日新聞 富山県版
16ミリフィルム283巻「お役に」
出張映写会で使用 魚津・小坂さん、夫の遺品寄贈
黒部市社協宇奈月支所に
小学校などへの出張映写会で使っていた16ミリ映画フィルム283巻が、公民館などで映画のビデオを上映している黒部市社会福祉協議会宇奈月支所に寄贈された。フィルムは、幼児や子ども向けが中心で、自然や娯楽映画などもある。同支所は「本物のフィルム映画を上映できる」と喜んでいる。
寄贈したのは、魚津市文化町の小坂陽子さん(76)。フィルムは、一昨年80歳で亡くなった夫の圭吾さんが所有していた。圭吾さんは1958年(昭和33)年に中国から引き揚げてきた後、富山市の映画会社に勤めた。約1年後に独立。県東部を中心に小学校や保育園、老人会などで約45年間、出張映写会をしてきた。
同支所が公民館などで、巡回映画「来て見てヤンバイ映画館」などを開催していることを知った陽子さんが「役立ててほしい」と、2月に寄贈した。16ミリフィルムは、いずれも箱入りで、相当な量があったため、同支所が1カ月以上かけkて整理し、データベース化した。
内訳は「日本昔ばなし」(25巻)「みなしごハッチ」「リボンの騎士」など子ども向けが全体の8割以上の234巻。「立山高原と黒部湖」「蒸気機関車」「日光」「尾瀬」など自然・ドキュメントが21巻。「近視の予防」「食品の正しい選択」など保健・衛生・教育が24巻。「アツカマ氏オヤカマ氏」(森重久弥、上原謙、小林桂樹出演)「無法松の一生」など娯楽が4巻。
同支所は、ビデオやDVDの映画約430本を所有しているが、16ミリフィルムの映画は初めて。現在、故障している16ミリ用の映写機を修理し、夏休みなどに、子供向けの上映会を企画している。
本波隆支所長は「これだけまとまった16ミリフィルムは貴重。映画のだいご味も違うと思うので、上映が楽しみ」と話している。
カラー写真(省略)
小坂さんから寄贈された16ミリフィルム=黒部市社会福祉協議会宇奈月支所
2008年(平成20年)3月23日(日)北陸中日新聞 富山県版
夢追人
福祉コラムが本に
黒部市社会福祉協議会宇奈月支所長
本波 隆さん(57)
ほんなみ・たかし 1950(昭和25)年12月、旧宇奈月町(現黒部市宇奈月町)浦山生まれ、国学院大学法学部卒業後、東京の通信機メーカーに就職。89年に帰省し、同年4月、旧宇奈月町社会福祉協議会事務局長に就任。旧黒部市、宇奈月町の合併に伴い、2006年3月から黒部市社協宇奈月支所長を務める。福祉コラムをまとめた冊子「おすそわけ」は同支所で希望者に無料配布している。
知らない人にも、あいさつをしていたあのころ。いただきものの蒲鉾(かまぼこ)を隣の家におすそわけ。
そうそう。お風呂だって近くの家へ入りに行ったこともありました。近所に困っている人がいれば、頼まれなくても顔を出していたのは、確かあの人−。
◇ ◇
地元の社会福祉協議会の情報誌で十五年書きつづった福祉コラムを、一冊の本にした。冒頭のくだりは、本の表題でもある一九九三年十月執筆のコラム「おすそわけ」からの一節だ。
「二百三十四編のコラムを書き残しましたが、この『おすそわけ』は私の思いを凝縮した作品なんです」と本波さん。当時はまだ社会に当たり前のように存在した「おすそわけ」の精神。あれから情報技術(IT)は目覚ましい発展を遂げ、社会のつながりは逆に希薄化した。「世の中から結いの心が失われていき、残念でなりません」と嘆く。表題に決めたのも、世の中が人間社会の原点に戻ってほしいとの願いからだ。
コラムを書き始めたのは、当時まだ身近な存在でなかったボランティアへの関心を集めるため、家庭の事情で八九年に東京からUターンし、旧宇奈月町社会福祉協議会に就職。そのとき初めて実感したのが、ボランティアに対する認知度の低さだった。
「ボランティアの存在が一般に広く知れ渡るようになったのは九五年の阪神・淡路大震災が契機ですから、それ以前はなじみが薄かったと思います。ましてボランティア活動を支援する社協(社会福祉協議会)のことなど、知っている人は本当に少なかったでしょう」と振り返る。
同社協が定期発行する情報誌の片隅に何気ないコラムでも載っていれば、手にした人が目を留めるかも−。そう思って九三年三月からせっせと書きつづった。「靴下の穴」や「スイッチ」「スリッパの向き」「救急箱」など身辺雑記が中心だが、「最近はネタ不足で苦労しています」と苦笑いする。
コラムを書く上で一つだけ決まり事がある。それは「説教めいたことを書かない」こと。自分が見たり聞いたり、体験したりしたことから書き起こし、読者に共感してもらえそうな”落ち”を付ける。「こうしなさい、とか押しつけがましい内容にならないよう心掛けています」
うれしいのは「あなたのコラム、読んでますよ」という読者からの声だという。「私が発したメッセージがちゃんと届いているんだと分かり、『よーし、次はもっと読んでもらえる内容にしよう』と気合いが入ります」
目下の目標は定年までコラムを欠かさないこと。「県内の社協の除法誌でこれだけ長くコラムを書き続けているのは、多分私だけでしょう。やめろと言われるまで継続したいですね」
(平井剛)
カラー写真(省略)
福祉コラムをつづった冊子「おすそわけ」を手にする本波隆さん=黒部市宇奈月町浦山で
2008年(平成20年)2月28日(木)朝日新聞 富山県版
福祉コラム15年
234編をまとめ自費出版
黒部市社協宇奈月支所長の本波さん
ボランティアの心 さりげなく
黒部市社会福祉協議会宇奈月支所長の本波隆さん(57)=写真、同市宇奈月町浦山=が、同協議会の情報誌に15年間、書き続けた福祉のコラム234編をまとめて、「おすそわけ」と題して自費出版した。身近にあるものや出来事、思い出などをつづりながら、ものの大切さや助け合いなど、ボランティアの精神をさりげなく説いている。
本波さんがコラムを書き始めたのは、旧宇奈月町社会福祉協議会時代の93年。年4回発行の同社協だよりに、1編200〜300字のコラムを4編ずつ掲載した。合併後は月1回発行の黒部市社協の「福祉くろべ」に、「温故知新」の欄を設けて書き続けている。
「福祉やボランティアについて、多くの人に考えてもらおう」との思いがきっかけだった。日常的なさりげない風景などから書き起こすように心がけた。
1回目は「靴下の穴」。昔は穴のあいた靴下だけでなく、ほころんだものをつくろっていたし、「靴下の穴は、もしかすると、心のどこかにあいた穴なのかも」と結んだ。ほかにも「石鹸(せっけん)」や「洗面器」「ポスト」など、懐かしい時代のものや情景などを取り上げている。
「おすそわけ」は、93年10月1日に掲載したコラム名から採った。隣家などへの「おすそわけ」が当たり前だった時代を振り返りながら、「あのころのことを思い出してみるのも悪くないかも知れません。そう、少しでも、人との痛みが分かるようになれれば」と記す。
A4版、83ページ。一冊にまとめるに当たり加筆、修正した。300部を印刷し、福祉関係者や全国の社会福祉協議会仲間に配布する。
本波さんは「思い出に浸るだけでなく、自分たちでできることに目を向けてもらえれば、との思いで書き続けた。題材探しに苦労するが、これからも続けた」と話す。
白黒写真(省略)
2008年(平成20年)2月19日(火)富山新聞 富山県版
黒部市社福協宇奈月の本波さん
15年間のコラム、1冊に 234編収録
日々の暮らしや風物詩
黒部市社会福祉協議会宇奈月支所長を務める本波隆さん(57)=同市宇奈月町浦山=は、一九九三年から社福協発行の情報誌に掲載されている自作のコラム二百三十四編を一冊にまとめ、二十日に発行する。タイトルは「おすそわけ」で、身近な題材をもとに、親しみやすい言葉でボランティア精神の大切さを説く内容となっている。
本波さんは旧宇奈月町社福協時代の九三年三月からコラムを担当し、社福合併後の現在も黒部市社福協発行の「福祉くろべ」でコラム「温故知新」を執筆中である。身近にある生活用品や風物詩などから話題を切り出し、最後の数行で簡潔に主張がまとまっている。
発刊に際し、全編を推敲(すいこう)、修正を加えた上で一冊にまとめた。「おすそわけ」は最も印象深いコラムのタイトルを採用したもので、近所付き合いの一コマを通して「少しでも、人の痛みが分かるようになれれば」と締めくくっている。
冊子はA4版、八十三ページで、社福協の本支所に置かれるほか、全国の社福協仲間にも配布する。本波さんは「社福協の情報誌を少しでも多くの人に読んでもらおうと始めた。これからも続けていきたい」と話している。
カラー写真(省略)
15年間書き続けたコラムを1冊にまとめた本波さん=黒部市社福協宇奈月支所
2008年(平成20年)1月12日(土)朝日新聞 富山県版
「男はつらいよ」「君の名は」・・・・
「どこでも」上映好評
黒部市社福協宇奈月支所
地域拡大、集会所・自宅出張も
黒部市社会福祉協議会宇奈月支所が、お年寄りらの希望に応じて集会場や個人宅に出張して映画のビデオを上映する「どこでもヤンバイ映写会」が好評だ。合併前の旧宇奈月町を対象に2年前に始まったが、今では旧黒部市内にも広がった。鑑賞者は、25回目の出張上映となった10日の同市宇奈月町の栗虫公民館で500人を突破した。
同支所は、01年6月から家の中に閉じこもりがちなお年寄りに映画を楽しんでもらおうと、旧町内7カ所の公民館などで巡回映画「来て見てヤンバイ映画館」を開催している。しかし、会場まで遠くて行けない高齢者や体の不自由な人もいることから、希望があれば少人数でも出張する「どこでもヤンバイ映写会」を06年1月に始めた。
「来て見て」と同様に、大型映写機とスクリーンなどを持ち込んで上映。同支所ではビデオ「男はつらいよ」シリーズなど48 本と、俳優阿藤快さんから寄贈されたビデオ37本を所有しており、「来て見て」で上映済み作品22本の中から選んでもらっている。
シリーズ初期の「男はつらいよ」のほか、「君の名は」や伴淳三郎と花菱アチャコの「二等兵物語」など懐かしい作品の人気が高い。
最初は、同支所管内の旧町内を対照にしていたが、旧市内からも要望が増え、一昨年11月から応じ始めた。出張した25回のうち13回は旧市内だった。上映場所は個人宅や集会場などさまざまで、旧市内では公民館が多い。一カ所での最小は2人、最多は46人で、平均約20人が鑑賞した。
500人を突破した栗虫公民館には11人のお年寄りが集まり、「男はつらいよ」の第1作(1969年作)を楽しんだ。
同支所の本波隆支所長は「どこへでも出張するので喜ばれている。旧市内からの要望も増えており、いずれは、旧市内でも『来て見てヤンバイ映画館』を定期的に上映できるようにしたい」と話している。
白黒写真(省略)
出前の映写会を楽しむお年寄りら、丸2年で500人を突破した=黒部市宇奈月町の栗虫公民館で
本波 隆(ほんなみ たかし)