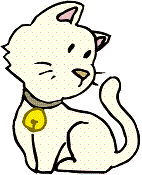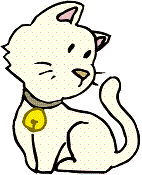2005年 本波 隆(ほんなみ たかし)福祉関係ニュース
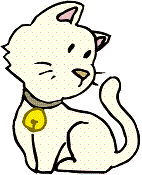
2005年(平成17年)12月30日(金)北日本新聞 富山県版
5人集まればどこへでも
好評ヤンバイ映画館
宇奈月町社福協
来月から拡充 名画を出張上映
宇奈月町社会福祉協議会(大坂吉郎会長)は来年一月から、高齢者の閉じこもり防止を目的とする巡回映画上映事業「来て見てヤンバイ映画館」を拡充する。五人以上集まれば自宅や集会所へ出張上映する「どこでもヤンバイ映写会」をスタート。巡回映画ではカバーできないエリアを中心に、懐かしの名画を大画面で鑑賞してもらい、介護予防につなげたい考えだ。
「ヤンバイ」は方言で「良かったね」「いい具体」などの意味。宇奈月町社協が四年前から、家に閉じこもりがちなお年寄りが外出し、仲間同士がふれあう機会を持ってもらおうと、無料での巡回映画事業に取り組んできた。
大型映写幕とプロジェクターなどを公民館などへ持ち込んで上映するほか、独自に制作した地元ニュース、簡単な体操も行い、楽しいひとときを過ごす。映画は「君の名は」(佐田啓二・岸恵子出演)「旗本退屈男」(市川右太衛門・片岡千恵蔵出演)など昭和二十年以降の名画が中心。事業の趣旨に賛同した俳優・阿藤快さんらから寄付を受けたビデオなどを活用している。
町内七カ所を年四回巡回してきたが、高齢者の足では会場まで遠くて行けなかったり、体の都合の悪い人もおり、少人数でも集まれば出向くことにした。地区のボランティアが上映し、参加者は使用済み切手や描き損じはがきの提供、折り紙づくりの手伝いなどのボランティアに加わってもらう。
同社協の本波隆事務局長は「映画観賞後に感想を語り合ったり、よもやま話をして楽しいひとときを過ごしてほしい」と話し、希望するグループを募っている。
カラー写真(省略)
「君の名は」など懐かしの名画の出張上映に向け、準備する宇奈月町社会福祉協議会の職員=宇奈月町浦山の事務所
2005年(平成17年)11月11日(金)BBTTV 18:16〜 富山県内放送
BBTスーパーニュース
合併で迫られる対応
一人暮らしの高齢者
2005年(平成17年)4月15日(金)北陸中日新聞 富山県版
寄付はがき1万枚に
宇奈月「お便りネット」
一人暮らしのお年寄り支える活動
全国から届く善意
丸八年で達成
宇奈月町内の一人暮らしのお年寄りあてに、はがきを書いてもらうボランティア活動「お便りネット」で、町社会福祉協議会に寄付されたはがきが一万枚を超えた。お年寄りの安否を確認する「高齢者見守りネットワーク事業」の一環で、はがきの提供を呼び掛けて丸八年で大台を突破した。
町内の一人暮らしのお年寄りは約二百人。はがきは、町内の保育所園児や小中学生、企業の社員らが書いて郵送している。郵便局員が配達する際には、お年寄りに異常がないか確認もしている。
お年寄りに届くのは、月一回ペース。はがきには絵が添えられていたり、健康への気遣い、学校生活の様子、行事への誘いなどがつづられており、お年寄りたちは楽しみにしているという。
町社協がお便りネットを始めたのは一九九七(平成九)年五月から。一年目は園児約七十人がはがきを書いていたが、ボランティアの輪は現在、約四百人に広がった。
はがきは、町社協に寄せられた未使用はがきや、書き損じはがきを新品に交換して使用。これまで延べ二百八十五人から寄付があった。
一万枚目を寄付したのは、札幌市の女性。十年ほど前に宇奈月町を訪れたことがあり、お便りネットはインターネットのホームページで知ったという。はがき百五十三枚とともに「心温まるボランティア活動を知り、うれしく思います。微力ながら、お役に立ちたい」と書かれた手紙が同封されていた。
町社協の本波隆事務局長は「多くのボランティアの善意に支えられ、これまで続いてきた」と感謝。問い合わせは宇奈月町社会福祉協議会−電話0765(65)9533−へ。
(広中康晴)
カラー写真(省略)
お便りネットで、子どもたちが一人暮らしのお年寄りに書いたはがき=宇奈月町社会福祉協議会で
2005年(平成17年)4月8日(金)北日本新聞 富山県版
宇奈月
「善意」1万枚超える
高齢者見守る お便りネット
285人はがき寄付
宇奈月町の一人暮らしの高齢者宅に定期的にはがきを送る町社会福祉協議会の「お便りネット」事業に対するはがきの寄付が、平成九年の事業開始以来一万枚を超えた。メッセージは、町の小・中学生や絵手紙教室の生徒、企業ボランティアが書いている。善意の寄付とボランティアに支えられ、地域全体で高齢者を見守る活動が続けられている。
お便りネットの寄付を受けた未使用のはがきや、書き損じはがきを新品と交換して使い、町内の一人暮らし高齢者約二百人に月一回程度送る。町内の保育所の園児や小・中学生、関西電力、黒部峡谷鉄道の社員らがボランティアでメッセージや絵を描き、郵送する。郵便局職員は届ける際に高齢者宅に異常がないかチェックする。
郵便局以外に、北日本新聞販売店や、電気、ガスなどの事業者も加わって高齢者宅を気遣う「見守りネットワーク」もある。
お便りネットは、同協議会の広報誌やNHKのホームページ・ボランティアネットで提供を呼び掛けている。町内外から延べ二百八十五人から善意のはがきが届いた。先ごろは北海道札幌市の女性から「心温まるボランティア活動をもっと広げてください」とのメッセージ付きで百五十三枚が届いた。
同協議会の本波隆事務局長は「善意でここまで続いた。今後も協力をお願いしたい」と話す。
白黒写真(省略)
園児や児童らがひとり暮らしの高齢者向けに送る宇奈月町社会福祉協議会の「お便りネット」事業=宇奈月町浦山 協議会事務局
2005年(平成17年)4月3日(日)富山新聞 富山県版
ひと登場
黒部との合併進める
宇奈月町社会福祉協議会事務局長
本波 隆さん(54)
黒部市と宇奈月町が来年三月に合併するのに伴い、同じ時期に同市社会福祉協議会と合併する準備を進めています。
合併に向けて力を入れたいことは現在、宇奈月町が社会福祉協議会が数多く行っている独自の取り組みを継続し、拡大することです。町社会福祉協議会は、他の社会福祉協議会がしていないことを積極的に行っています。
例えば在宅高齢者見守りネットワーク、巡回映画上映会などです。今月の同上映会からは、町社会福祉協議会が考案した老化防止体操も行われます。開会式に約千人が集まる秋のボランティアの集い「町民ふれあいまつり」も特筆される行事です。
国を始め行政が財政的に苦しんでおり、合併後の補助金増額は見込みにくい状況です。しかし、黒部市社会福祉協議会と協議し、これらの事業を企業や他の団体と連携してでも継続したい考えです。
(宇奈月町浦山)
カラー写真(省略)
2005年(平成17年)3月19日(土)讀賣新聞 富山県版
『ヤンバイ体操』 来月ビデオ上映
「青い山脈」に乗せ気軽に
宇奈月町社協
宇奈月町の社会福祉協議会は、お年寄りになじみがある映画の主題歌とともに気軽に体を動かせる体操のビデオを制作中だ。ビデオは4月から、同社協が町内で開いている上映会「来て見てヤンバイ映画館」の会場で流される。関係者は、体操をお年寄りに覚えてもらって、老化防止のために自宅にいる時も取り組んでもらえれば、と期待している。
同社協は、月2回のペースで町内7か所を巡回して上映会を開いている。体操の映像を上映しようというアイデアが浮かんだのは作年秋ごろ。
映画の前に、社協職員が取材した「宇奈月ニュース」を毎回3分ほど流しているが、その中で、音楽に合わせて体操している様子を見た会場のお年寄りが一緒に体を動かし始めるシーンが複数の上映会場で見られれた。本波隆・同社協事務局長は「これはいけるぞと思った」と明かす。
体操の振り付けは、同社協職員の河村美子さん(57)が約1か月かけて完成させた。河村さんは、社協と同じ建物にはいっている町老人福祉センターでお年寄りに体操を教えるなどしている。
出来上がった体操は、ラジオ体操を参考に、肩回しや体の横ひねり、もも上げといった簡単な動きが中心で、映画主題歌「青い山脈」のメロディーに合わせたもの。バランスを崩さないよう、ゆっくりした動きを心掛けるとともに、飽きられないよう足のつま先の開閉や肩たたきを取り入れたのが特徴という。
ヤンバイは方言で「よかったね」の意味。上演会にちなみ「ヤンバイ体操」と名付けられた。
ビデオ収録は18日、町老人福祉センターで行われた。河村さんのほか、町内のお年寄りたちも出演した。
河村さんは「『楽しかった』と言ってもらえれば」と願っている。
カラー写真(省略)
ビデオ収録のため、河村さん(左)と一緒に体操を行うお年寄りたち=宇奈月町の町老人福祉センターで
2005年(平成17年)3月17日(木)NHK総合TV 21:15〜21:58 全国放送
難問解決!ご近所の底力
わが町を終(つい)のすみかに
妙案再び
2005年(平成17年)2月27日(日)BBTTV 9:00〜 富山県内放送
きときとキッズ!
フォーカスイン
始めてみませんか?ボランティア
2005年(平成17年)2月23日(水)北陸中日新聞 富山県版
地震、水害対策に重点
ふくし災害マニュアル発行 昨年の被害踏まえ
宇奈月社福協
地震や災害などへの備えをまとめた「ふくし災害マニュアル」を、宇奈月町社会福祉協議会が今年も発行し、町内全戸に配布した。一九九五年一月の阪神大震災を機に作製して以来、毎年少しずつ内容を更新しながら発行を続けて十年目。同協議会は「普段からの備えが大切」と呼び掛けている。
マニュアル作製は、阪神大震災直後にボランティアとして神戸市入りした同協議会事務局長、本波隆さん(五四)の経験を生かした。「災害が発生してから準備しても遅い」と本波さん。最初のマニュアルとして「災害時の行動十か条」と、避難場所などをまとめて翌九六年三月に発行した。
十回目の今年は、新潟県中越地震や台風、大雨の被害が相次いだ昨年を踏まえ、地震や水害の備えに重点を置いた。家具の固定など日ごろの地震対策をはじめ、冠水した場合の注意点として「長靴は水が入って歩きにくくなる」「歩くことができる深さは、男性七十センチ、女性五十センチ」などと具体的に示している。
非常持ち出し品や非常備蓄品のチェックリスト、ボランティア活動例を紹介するページも。A4版、八ページの二色刷りで、お年寄りにも見やすいよう、文字を大きくした。
同協議会では、マニュアルで災害対策を呼びかけるとともに、お年寄りや障害者ら災害弱者の情報把握にも努めている。九九年三月に「地図情報システム」をスタート。パソコンの地図画面上に「一人暮らし」「寝たきり」などが色分けされ、緊急連絡先などが分かる仕組みとなっている。
「大震災直後は、困っている人がどこにいるのか分からなかった」と振り返る本波さん。同協議会では現在、約九百件の情報を把握。災害発生時は、ボランティアらに必要な情報を伝え、安否確認などに役立てる。情報は民生委員らが調べ、毎月更新している。
(広中康晴)
カラー写真(省略)
発行を続けて10年目を迎えた「ふくし災害マニュアル」=宇奈月町で
2005年(平成17年)2月9日(水)讀賣新聞 富山県版
一人暮らしのお年寄りに声をかけたい−
映画の巡回上映
チラシ配布100日
宇奈月町社協・本波さん
町内の公民館などを巡回して映画を上映する「来て見てヤンバイ映画館」の開催前に、主催している宇奈月町社会福祉協議会の本波隆事務局長(54)は毎回、自転車か徒歩で一軒ずつチラシを配っている。一人暮らしのお年寄りの安否確認も兼ねている。八日のの音沢公民館での上映会に向けた配布でちょうど百日になったという。
上映会は四年前から月二回のペースで町内七カ所を巡回している。「ヤンバイ」は県東部の方言で、「良かったね」という意味。家に閉じこもりがちなお年寄りに外出してもらうのが目的。これまでに上映されたのは「釣りバカ日誌」などの人気作品十二編。上映回数は八十七回に上る。
チラシは、上映会開催の数日前に対象地区の全戸に配布している。作業は半日で終えたり、二日にわたったりする。今回は三日に行われた。本波さんは「一人暮らしの高齢者にも声をかけようという発想で始めました。配布の際は、郵便物がたまっていないかといったことにも気をつけています」と話す。
一会場あたりの平均動員数は二十六人。上映は平日昼間に行われ、お年寄りが大半という。
この日、音沢公民館で上映された映画は「男はつらいよ 寅次郎忘れな草」。雨天のためか出足が悪く、開演五分前になっても観客は二人だけ。自宅前で直接チラシを受け取ったというお年寄りの女性が「少なくて申し訳ないね」と気をつかうと、「一人も来なくても上映しますよ」と本波さんが笑顔で応えた。
上映時間ぎりぎりに「常連客」の一人で近くの佐々木宗作さん(82)が駆け込んできた。佐々木さんは「(チラシを)わざわざ配りに来てくれているから見に行かなければと思う。いつも楽しみにしています」と話していた。
白黒写真(省略)
公民館で映画を楽しむ地元のお年寄りら(宇奈月町音沢の音沢公民館で)
2005年(平成17年)2月7日(月)朝日新聞 富山県版
宇奈月町社協の「ふくし災害マニュアル」
防災の備え訴え10年目
災害への備えや心構えを記した宇奈月町社会福祉協議会の「ふくし災害マニュアル」
が、10年連続で町内の全世帯に配布された。阪神大震災を機に「災害に対する意識を持ち続けてもらおう」と毎年、新しい内容を盛り込んでいる。安否確認や救助に即応できるようにと、災害弱者の自宅や家族構成などがわかる地図情報システムも99年に構築、万が一に備えている。
大震災直後に、ボランティアとして神戸市に駆け付けた同協議会の本波隆事務局長(54)の経験がきっかけだ。被災地で困っている人がどこにいるのか、困っている中身は何かがなかなか分からなかった。「災害が発生してから準備しても遅い。普段から災害に備え、訴え続けることが必要」と本波事務局長。
「災害マニュアル」は、大震災の翌年の96年3月に初めて発行した。B5版(2年目からA4版)の8ページの2色刷り。安全対策や非常持ち出し品の準備、火の始末、徒歩での避難など、災害時の行動10カ条や避難場所の写真をはじめ基本的な心構えをまとめた。
以来、ボランティア活動や落ち着いて行動するためのアドバイスなど内容を毎年、少しずつ変えて発行し続けている。避難場所一覧や行動10カ条は毎回、掲載している。
10回目の今回は、集中豪雨や新潟県中越地震などが相次いだ昨年を教訓に、「地震と水害に備えて」との副題を付けた。家具の固定など地震時の備えや、水害の際の対策や避難時の注意点、非常用品のチェックリストなどを掲げた。高齢者でも見やすいようにと、文字も大きくした。約2100世帯と公民館や学校、企業などに配布した。
災害弱者の地図情報システムは、町内の住宅地図と災害弱者情報を組み合わせ、99年3月に立ち上げた。
地図上に「一人暮らし」「二人暮らし」「寝たきり」などの印が色分けされ、該当する家をクリックすると、住所や名前、年齢、緊急連絡先などが表示される。事務局に設置されているパソコンには約900件の情報が組み込まれている。こうした情報は同協議会が管理しており、職員以外はアクセスができない。
災害発生の際は、98年に発足させた災害情報ネットワークに加盟する官公庁やボランティア、民生委員児童委員などに必要な情報を伝え、救助や安否確認に役立てる。災害弱者の情報は、民生委員児童委員が調べ、毎月更新している。
本波事務局長は「災害はいつ起きるかわからない。阪神大震災の経験から切れ目なく注意を呼びかける必要性を痛感した。対策に終わりはなく、これからも訴え続けていきたい」と話す。
白黒写真(省略)
10年連続で発行された災害マニュアル=宇奈月町浦山で
2005年(平成17年)2月2日(水)北陸中日新聞 富山県版
巡回映画の楽しさ再現
宇奈月町社福協
お年寄り向け、月2回上映
戸別訪問のチラシ配布 あすで100日目に
家に閉じこもりがちなお年寄りに楽しんでもらおうと、宇奈月町社会福祉協議会が巡回映画事業「来て見てヤンバイ映画館」を始めて3年8カ月。上映する映画の手作りチラシを社協職員が戸別訪問して届けており、3日に予定されている訪問で、配布日数は100日目を超える。
(広中康晴)
ヤンバイ映画館は、映画館に足を運ぶことのなくなったお年寄りに、懐かしい映画を見てもらい、外出機会を増やすことで介護予防に一役買う狙い。お年寄りが出かけやすいよう、地元の公民館などを月二回、巡回しながら無料上映している。
「ヤンバイ」とは「案配」がなまった県東部の方言。地元では「いい案配」が転じて「良かったね」という意味で使われる。事業名には、かつて地域で一緒に見た巡回映画の楽しさ、和気あいあいとした雰囲気を再現しよう−という思いを込めた。
会場は、下立、愛本、内山、音沢、浦山の各公民館をはじめ、町福祉センター、栃屋郷土館の計七カ所。上映の数日前には、社協事務局長の本波隆さん(五四)が、地域ごとに全世帯を一軒ずつ訪ね、チラシを配りながら来場を呼びかけている。
これまでの上映回数は八十七回。一九六九(昭和四十四)年から始まった「男はつらいよ」シリーズをはじめ、「釣りバカ日誌」シリーズなど計十二作を上映してきた。古くは五八年の「旗本退屈男(はたもとたいくつおとこ)」「二等兵物語」などもあり、お年寄りを喜ばせた。
チラシの配布対象は、町内のほぼ全域の約二千世帯。これまでに約二万枚のチラシを配り、延べ二千三百二十八人が映画を見た。会場では、お年寄り同士の触れ合いにも一役買っている。
次回は、八日午後一時半から音沢公民館で上映する「男はつらいよ 寅次郎忘れな草」。社協では上映を前に、チラシ制作などの準備に励んでいる。
カラー写真(省略)
次回上映作のチラシ制作に職員が励んでいる−宇奈月町社会福祉協議会で
2005年(平成17年)2月1日(火)BBTTV 18:17〜 富山県内放送
スーパーニュース
防災キャンペーン
災害弱者対策・宇奈月
2005年(平成17年)1月18日(火)チューリップTV 18:18〜 富山県内放送
ニュースの森チョイス
被害を最小限に
大震災を教訓に地域が取り組みはじめた備えとは・・・・宇奈月
災害から学ぶこと
災害に備え地域のつながりを
2005年(平成17年)1月17日(月)北日本新聞 富山県版
阪神大震災から10年
6割超「今後も支援を」
(一部省略)
宇奈月町社福協
震災機に災害弱者地図
情報を一元化
全国から注目
平成七年二月七日、神戸市灘区の市営住宅、阪神大震災の発生から三週間が過ぎていたが、八十歳の母親と、足に障害を持つ五十六歳の息子が暮らす家では、倒れたままのたんすと仏壇のすき間で寝泊まりをし、食事にも窮していた。
「こんな大変なのに、助けを求める声を上げることができない災害弱者がいる」。ボランティアとして、この家の片づけを手伝った宇奈月町社会福祉協議会の本波隆事務局長(五四)は驚いた。もし、高齢者の多い宇奈月町で地震が起きたら同じ事が起きないか、頭を悩ませながら引き上げた。
あれから十年、宇奈月町浦山の同協議会事務局には、災害弱者の自宅がすぐに分かる地図情報システムのパソコンが備えられている。集中豪雨や地震が続いた昨年は、全国の被災自治体から問い合わせが相次いだ。
システムは、地図と災害弱者情報がドッキングしたもの。地図画面上に「一人暮らし」「二人暮らし」「寝たきり」などの印が色分けされ、クリックすると名前や年齢、電話番号、緊急連絡先などの情報が表示される。
万一の際には、災害情報ネットワークに加盟する民生委員児童委員やボランティアらをはじめ、郵便局、寺院、土木事業者などへプリントして渡し、救助や安否の確認をしてもらう。災害弱者の情報は民生委員児童委員が調べたデータを基に、毎月、更新している。
システムを視察した福岡県稲築町社会福祉協議会の木山淳一事務局長は「新潟県中越地震の被災地も視察したが、いざという時に、ビジュアルに分かる地図の必要性を痛感した」と言う。
宇奈月のネットワークには近く消防分団も加わる予定で、支援態勢が厚みを増す。本波事務局長は「ようやここまでこぎ着けた。だが、対策に終わりはない。更新したり、訴え続けたりすることが何よりも大切」と話す。
カラー写真(省略)
地図情報システムのデータ更新を指示する本波事務局長=宇奈月町浦山の町社会福祉協議会事務局
本波 隆(ほんなみ たかし)