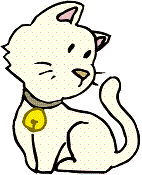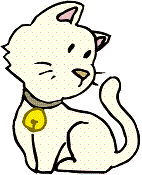1997年 本波 隆(ほんなみ たかし)福祉関係ニュース
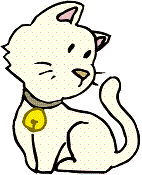
1997年(平成9年)9月23日(火)北日本新聞 富山県版
児童もボランティア参加
きょう宇奈月 ふれあい祭り
300人が運営協力
宇奈月町内の企業、団体などがボランティアで運営する「町民ふれあいまつり」が十五年目を迎える。今年は二十三日午後一時から宇奈月中学校グラウンドで開き、過去最高の四十一店が出店、車いす介助を行う宇奈月小児童ほか約三百人がボランティア参加する。
祭りは昭和五十八年に始まり、最初は十一店が出店したが、昨年までに三十九店に増加。参加者も町民の三分の一以上の二千五百人が訪れるまでになった。
同町社会福祉協議会を事務局に、運営には青年団や婦人会などが加わる。今年は宇奈月小から「協力したい」と申し出があり、五、六年生二十七人が特別養護老人ホーム「おらはうす宇奈月」の入所者の車いす介助を行う。町外の小学生や県外の女性からも参加申し出があった。
当日は焼きそばやアイスクリームなど模擬店が並ぶお楽しみコーナー、ゲームやおもちゃの手作りコーナーなどがあり、参加者に各店で楽しめる四枚一組の引換え券を無料で配る。保育所年長児の親子フォークダンス、愛本小の鼓笛隊演奏も披露される。
町社会福祉協議会の本波隆事務局長は「祭りが老人や障害者を含め町民みんながふれ合うきっかけになれば」と話している。
1997年(平成9年)9月4日(木)KNBTV 18:30~ 富山県内放送
ニュースプラス1
老いを支えて
見守りネットワーク
1997年(平成9年)6月29日(日)北日本新聞 富山県版
こころ支え合う
地域福祉や教育現場、医療現場など心の病や問題にかかわりを持つ人たちに、それぞれの立場から連載「こころ支え合う」の感想や意見を寄せてもらった。
(一部省略)
社協でもできることがある
宇奈月町社会福祉協議会事務局長
本波 隆さん(46)
連載を読んで、精神障害者への福祉が身体、知的障害者に比べて遅れていることを痛感した。地域福祉の一翼を担う社協だが、これまでは目に見える障害にしか手を差し伸べてこなかったというのが実情だ。
精神障害者も地域の一員であることに変わりない。地域住民が心を支え合っていくために、社協が精神障害者の福祉にもかかわっていくべきだと思う。
心の病への偏見は病についての知識がないことが原因の一つになっている。偏見をなくすため、社協が啓もう活動をすることはできる。ほかにも何らかの形で携われることがあるはずだ。
また、宇奈月町社協で作成した災害マニュアルも、避難誘導など災害直後の対応策は書かれているが、その後の住民の心のケアまでは触れなかった。今後の課題にしたい。
カラー顔写真(省略)
1997年(平成9年)6月5日(木)NHKETV 13:00~13:30 全国放送(再放送)
すこやかシルバー介護
シリーズ・手作りの在宅ケア
①老人の見守りネットワーク
出演者 立正大学教授 小笠原 祐次
富山県宇奈月町社協 本 波 隆
きき手 増渕 路子
2040-183
収 録 1997年(平成9年)5月22日(木) NHK放送センターCT111 10:00~17:30
1997年(平成9年)6月4日(水)朝日新聞 テレビ番組欄
すこやかシルバー介護
★教育 夜7・30
地域に根づいた「手作りの在宅ケア」をシリーズで紹介する。一回目は富山県宇奈月町の「見守りネットワーク」。郵便、新聞、牛乳の配達人が協力し合い、町内に住む一人暮らしのお年寄りに異変がないかを確認する。
1997年(平成9年)6月4日(水)北日本新聞 テレビ番組欄
すこやかシルバー介護
教育後7・30
宇奈月町の「見守りネットワーク」を取り上げる。郵便、新聞、牛乳の配達人が協力し、配達の際に町内に住む一人暮らしのお年寄りに異変がないかを注意する。昨年四月からは新たに電気、ガス、水道の検針者、警察官が加わった。
また、最近では小学生の”手紙を出す運動”などの気運も出ており、住民の意識にも著しい変化が見られるという。
1997年(平成9年)6月4日(水)讀賣新聞 テレビ番組欄
すこやかシルバー介護
(教育-後7・30)
高齢者のための手作りの在宅ケアの試みを、それぞれの地域から報告する。四回シリーズ。
富山県宇奈月町では、郵便、新聞、牛乳の配達人が協力して、町内に住む一人暮らしの高齢者を対象に、配達の際に異変がないかをチェックする”見守りネットワーク”をつくっている。
1997年(平成9年)6月4日(水)NHKETV 19:30~20:00 全国放送
すこやかシルバー介護
シリーズ・手作りの在宅ケア
①老人の見守りネットワーク
出演者 立正大学教授 小笠原 祐次
富山県宇奈月町社協 本 波 隆
きき手 増渕 路子
2040-183
収 録 1997年(平成9年)5月22日(木) NHK放送センターCT111 10:00~17:30
1997年(平成9年)4月28日(月)毎日新聞 全国版(生活いきいき家庭)
出歩けないお年寄りに
ホッカホカ出前ビデオ
見たかった実家の風景、祭りの舞・・・・・・懐かしい日々が、よみがえる
町民総出で撮影、届ける
黒部川沿いに開ける富山県宇奈月町。春らんまんののどかな町で、体が不自由な高齢者や障害者の希望を聞いてビデオを撮影、自宅まで届けて見てもらう「ふくし出前ビデオ」が誕生し1年たった。ボランティアが手づくりのその出前は、ホッカホカ。温かい湯気が立っていた。 【青戸三千彦】
窓辺に人影が見える。近付いた。やはり藤川直芳さん(78)だ。待ちわびていたのだった。
「今日はな、あんたに明日(あけび)の稚児舞を見せよと思て。昨日、撮影したばっかりのがぁう、持って来たがいやね。さあすぐ見っしゃるけ」
稚児舞のビデオを出前してきたボランティア、橘理吉さんが早速テレビにセットする。橘さんは、藤川さんとは同年。お互い稚児舞には懐かしい思い出を持っている。看護婦の経験がある中岡よしえさん(73)は血圧計を取り出した。
「稚児舞の日は学校が半ドン、楽しみでな」。「昔は仁王門からずーっと道の両側に出店が並んどったもんやちゃ」。遠い日の思い出がよみがえる。「ゴォーン」。「鐘の音を聴いたちゃぁ何となぁく、ありがたぁーなるがいちゃ」。ベッドに正座した妻のマスさんが(79)がつぶやく。
藤川さんは、息子さんの家族と別居し、富山県下新川郡宇奈月町浦山の町営住宅でマスさんと2人暮らしだ。車いすの生活はもう26年。「40年前トンネルが落盤し右足に大けが。そして、26年前、木から落ちてしもたがいけど」
評判の元気者だった。しかし、車いすにしばられた今は思いだけが先に立っても行動がままならない。遠い昔がますます懐かしい。そんな時、宇奈月町社協が1年前から始めた「ふくし出前ビデオ」の話を聞き、町内の法福寺に伝わる『明日稚児舞』を見たい!と訴えたのだった。
「在宅老人は外との交流を断たれています。地域と交流できないものか、知恵をしぼった結果がこの『ふくし出前ビデオ』です」。同社協の本波隆さん(46)。ビデオの出前そのものよりは、ボランティアと高齢者とが出前を介して温かく交流することに本当の意味がある、と話すのだ。
過疎化が進み、今、同町(人口6800人)は65歳以上の老人が約1600人。その10人に1人がひとり暮らしだ。地域住民全員が孤独な老人の存在を人ごとでは済まされない。『ふくし出前ビデオ』のボランティアは、さまざまなところから相次いだ。
かつての職場も
前日、藤川さんが見た稚児舞を撮影したのは黒部峡谷のトロッコ電車運転手、岩田博和さん(28)。子どものころ、ぼくも稚児舞を踊ったような記憶があるあるみたいだ」という。リポーターは主婦の大橋朋子さん(34)、説明は「明日稚児舞保存会」会長を28年間も務めた山本恵通さん(78)が買って出た。
これまで24本のビデオを撮影。かつての職場を訪ねた、たった一人のための作品もある。「昔の同僚が『おい元気か。頑張れ』と寝たきりのその人を励ますのです」「それを見て、もう目を真っ赤にして、泣きじゃくるのです」。同社協の岩坂美代子さん(41)と池田富士子さん(38)が打ち明けてくれる。
女性の場合、ほとんどが嫁ぐまでを過ごした実家やその周辺をぜひ見たいと訴えるという。
同社協はこの「ふくし出前ビデオ」に続き、入院の高齢者をボランティアが定期的に訪ね、買い物や、自宅へ洗濯物を届けて着替えを取って来たり、雑事を何でも引き受ける「まごころ定期便」を、25日にスタートさせた。これも、不自由な高齢者と地域住民との交流をはかる願いをこめたものである。
白黒写真(省略)
法福寺に伝わる明日の稚児舞
<明日稚児舞>1592年から始まったという。小学生男児4人の稚児は4月11日から練習に入り18日の本番まで魚肉は食べず土も直接踏まない。国の重要無形民俗文化財。
白黒写真(省略)
稚児舞のビデオを映す前に血圧測定。ボランティアの中岡さんは元看護婦だ。
1997年(平成9年)4月25日(金)朝日新聞 富山県版
「まごころ定期便」発車
宇奈月できょうから
入院患者手助け
社会福祉協 病院にポスト設置
ボランティア友の会が協力
外での用足しや話し相手に
定期的に病院などを訪問し、外出できない入院患者の代わりに買い物などを手伝い、話し相手などにもなる「まごころ定期便」を、二十五日から宇奈月町社会福祉協議会が始める。同町ボランティア友の会(笹谷志賀子会長)が協力し、善意の生活ナビゲーターとなる。
患者は入院していても外へ出ていろいろ用を足したいことがある、と考えたのが始まり。特に独り暮らしのお年寄りなどは不便を感じるのではと、ボランティアが手足になって用事を代行することを企画した。
このシステムを希望する病院内に「まごころ定期便」のポストを設ける。入院患者は用意されているカードに「部屋番号、名前、希望内容」を書き込み、ポストに入れる。
ボランティアが週一回訪れ、患者の注文に応じて買い物などをして届けたり、郵便物を送ったりする。患者に代わって病院と自宅を往復し、洗濯物を届けもするが、これは地理が分からないことなどから町内に限る。
明日温泉治療所では、二十五日には、長袖の下着や髪のくしなどの買い物や理髪ボランティアにきてほしいといった希望が出ているという。買い物の場合は、預かり書を出し、品物のレシートを持ち帰り精算する。
ボランティアはほとんどが同町内の主婦だが、趣旨に賛同した魚津市や入善町からも手伝いたいという申し出が寄せられている。
社会福祉協議会の本波隆事務局長は「徐々にいろんな要望が出てくると思うが、できる限り対応していきた。全国的にも珍しいのではないか」と、その効果に期待している。
白黒写真(省略)
手作りの「まごころ定期便」ポスト=明日温泉治療所で
1997年(平成9年)1月27日(月)北陸中日新聞 富山県版
クローズアップ
宇奈月町社会福祉協「望みかなえビデオ」
寝たきり高齢者に交流の場
町住民がボランティア
希望の身近な活動収録
地域住民がボランティアで、寝たきりのお年寄りの希望する町並みや知人の姿をビデオに収録し届ける。宇奈月町社会福祉協議会が昨年春から始めた「望みかなえビデオ」。体が不自由なため満足に外出できず、周辺住民と触れ合う機会もほとんどない寝たきりの人との接点づくりの一つとして導入された事業は、人口七千人余りの小さな山間の町に根づき始めている。(黒部通信局・小蔵裕)
新学期が始まり、校舎の窓のすき間から子供たちの元気な声が漏れてくる宇奈月小学校。冬の晴れ間がのぞいたある日、同校正面玄関前で、数人がビデオ撮影に取り組んでいた。マイクを手にした大橋朋子さん(三四)の問いに答え、学校周辺の移り変わりを説明する上野秀雄さん(七〇)。ビデオカメラのレンズを通して二人をとらえる大田佳昭さん(五八)。主婦、会社員と普段の職業は違えど、いずれも宇奈月町在住で「望みかなえビデオ」制作に携わるボランティアの人たちである。
脳梗塞(のうこうそく)で寝たきりとなった同町下立の男性(六九)が、町社会福祉協議会に依頼したビデオ撮りは、学校近くの上野さん宅に場所を移し、さらに一時間余り続けられた。
二十年余り趣味でビデオをまわす大田さんは「撮影は顔が出ない裏方だが、ビデオを見る人が美しく見えるよう工夫しながら撮っている。本来、裏方が生に合ってんだ」と笑う。リポーター姿も板についてきた大橋さんは「ビデオを見て、喜んでもらえた時は、本当にやりがいがある」といい、依頼者の男性から農学校時代の同級生として登場を求められた上野さんも「何を差し置いてでも引き受けたいという気持ちだった」と話す。こうした人たちの協力で、ビデオ作りは進められている。
望みかなえビデオを発案した、町社会福祉協議会の本波隆事務局長は「地域住民が寝たきりの人を訪ね、温かい交流ができる方法はないかと考えた結果、出てきたのがビデオ」と事業開始のきっかけを語る。されに、ビデオの内容について「全国ニュースなど遠いところのできごとはテレビや新聞がある。しかし、十軒先の家に赤ちゃんが生まれた、昔の友達が家を新築したなど、近いところの話題を見たいのではないかと気付いた」という。
事業開始前に本波事務局長は、町内の寝たきりや重度障害者の家を一軒一軒訪問し、事業の内容を説明した。ビデオカメラやテープ、依頼者の家で上映する際のビデオ付きテレビなどは、機材はすべて町社会福祉協議会が用意。依頼者の負担はない。
「手探り状態でのスタートだったが、依頼者の評判もよく、ボランティアの協力など予想以上の広がりとなった」と本波事務局長。撮影やリポーター、編集役などボランティアは現在十数人となった。「あとは、ビデオをきっかけに、寝たきりの人と住民の交流が深まれば」と願う本波事務局長。その願いも、ビデオに出演した上野さんが「これを機会に一度(依頼者宅)を訪問しようと思っている」と話すように、着実に実を結びつつある。
白黒写真(省略)
ビデオを通じて依頼者に語り掛ける上野さん(左)とリポーターの大橋さん(中央)=宇奈月町内山の上野さん宅で
本波 隆(ほんなみ たかし)