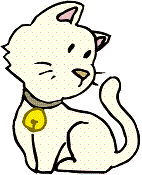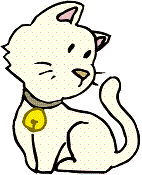1995年 本波 隆(ほんなみ たかし)福祉関係ニュース
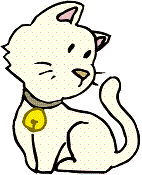
1995年(平成7年)11月4日(土)NHK総合TV 10:00〜10:30 全国放送の富山県内再放送
週刊ボランティア
湯の町のふれあいボランティア
〜富山県・宇奈月町〜
キャスター 広瀬 久美子
ゲスト 早瀬 昇(大阪ボランティア協会事務局長)
ゲスト 本波 隆(宇奈月町社会福祉協議会事務局長)
リポーター 秋野 由美子(NHK富山局)
コード 306−21550
収録日 1995年(平成7年)10月24日(火)宇奈月国際会館セレネ小ホール
1995年(平成7年)11月3日(金)」北日本新聞 テレビ番組欄
NHK教育テレビ
みもの
週刊ボランティア
教育7・20
宇奈月町の社会福祉協議会では、高齢化社会を前に町ぐるみのボランティア活動を進めている。独り暮らしのお年寄りのため副食サービス、墓参り同伴などのメニューをつくり町民にボランティアを呼び掛けているほか、地元企業の社員による送迎ボランティア、寝たきりのお年寄りを訪問、診察する開業医のボランティアなどが行われている。同町でのボランティアを広げる試みを紹介しながら、今後のボランティアの考える=写真
カラー写真(省略)
1995年(平成7年)11月3日(金)」富山新聞 テレビ番組欄
NHK教育テレビ
みもの
富山県宇奈月町のボランティアの試みを紹介する
【NHK教育7・20】
富山県宇奈月町の社会福祉協議会では、高齢者社会を前に、町ぐるみのボランティア活動を進めている。独り暮らしの高齢者のための副食サービス、墓参り同伴などのメニューをつくり町民にボランティアを呼び掛けているほか、地元企業の社員による送迎ボランティア、寝たきりの高齢者を訪問などが行われている。
カラー写真(省略)
1995年(平成7年)11月3日(金)」讀賣新聞 テレビ番組欄
NHK教育テレビ
週刊ボランティア
(教育−午後7・20)
富山県宇奈月町では”超高齢化社会”を目前に、町ぐるみのボランティア活動を進めている。一人暮らしのお年寄りのための副食サービス、墓参り同伴ボランティアなどさまざまなメニューを作り、町民に参加を呼びかけている。山間の温泉町の試みを通し、これからの地域ボランティアを考える。
1995年(平成7年)11月3日(金)NHK教育TV 19:20〜19:50 全国放送
週刊ボランティア
湯の町のふれあいボランティア
〜富山県・宇奈月町〜
キャスター 広瀬 久美子
ゲスト 早瀬 昇(大阪ボランティア協会事務局長)
ゲスト 本波 隆(宇奈月町社会福祉協議会事務局長)
リポーター 秋野 由美子(NHK富山局)
コード 306−21550
収録日 1995年(平成7年)10月24日(火)宇奈月国際会館セレネ小ホール
1995年(平成7年)10月10日(火)とやまの生涯学習No.165 富山県民生涯学習カレッジ
魚津地区
ボランティアってなぁに
〜自然や人へのやさしさを求めて〜魚津市
ボランティア体験活動養成講座の開講式でのことである。
「ふだんから仲良くしておれば困った時助け合える。ボランティアって決して難しいことではないのですよ。あいさつをすること。勉強すること。お手伝いすること。『はい』と返事することもみなさんにできるボランティアなのですよ。」
講師の本波隆先生(宇奈月町社会福祉協議会事務局長)の具体的な話に、参加した子どもたちの目が輝いた。
ボランティアって何かな、自分たちにもできるかなと心配しながら聞いていた子どもたちも、これなら自分たちにもできると確信したようであった。
その後、町内小学校の障害をもつ子どもを招いての宿泊交流会で、グランドでサッカー遊びをしていたときのこと、同じ小学校から参加した子どもどうしで言い争いになった。そのとき一人の子どもがすかさず、「ボランティアにきとらいから、ケンカできんがいじゃなぁ。」とたしなめた。あのときの、あの話が、子どもの心に生きて働いているのかなと、ちょっと安心した。その後、子どもたちは、沢杉林の清掃活動、特別養護老人ホーム寿楽苑の訪問活動、プレゼントづくりなど、自然へも、人へも、精一杯のやさしさを発揮することができた。
(入善町教育委員会 広田 登)
白黒写真(省略)
特別養護老人ホーム寿楽苑にて
1995年(平成7年)8月21日(月)朝日新聞 富山県版
リポート富山
「ありがとう」の一言を報酬に
センター設け町民総ぐるみボランティア
宇奈月
中学生も施設訪問
福祉地図を作製
宇奈月町で、社会福祉協議会を中心にしたボランティア活動が活発だ。今年六月、北陸三県で初めて同協議会内にボランティア情報センターを設置。寝たきり老人や重度障害児(者)などの把握、パソコン通信によるボランティアの情報交換など、さまざまな機能を持つ。まだ、特別養護老人ホーム「おらはうす宇奈月」では施設ボランティア活動、地区福祉活動推進委員会も在宅寝たきり家庭訪問サービスに取り組むなど、「町民ぐるみ」の活動ぶりだ。(工藤 義亮)
同協議会は一九九一年から、民生委員・児童委員の協力で寝たきり老人や重度障害児(者)、一人暮らしや二人暮らしの老人、母子家庭など十二項目の対象者を、パソコンに入力してきた。
この四月には、町のボランティアに関する情報を全国発信したり、全国のボランティア情報を得たりするため、NHKボランティアネットに加入。災害に見舞われて援助が必要な自治体との情報交換や、ボランティアの派遣などをスムーズに行える態勢を整えた。
これらの事業がある程度整った六月、同情報センターをスタートさせた。寝たきり老人や重度障害児(者)など家庭別に色分けした福祉地図を作製。同センターと民生委員・児童委員が保管、要援護家庭の把握に努めている。同協議会の本波隆事務局長(四四
は「福祉地図は全国でも例がないと思う」と胸を張る。
八八年年二月に発足した地区福祉活動推進委員会の活動も目覚ましい。委員は町内六地区に計九十人。在宅寝たきり家庭訪問サービスは、医師(年四回)、看護婦(年六回)、保健婦(同)、ボランティア(年十二回)が希望する家庭におもむく。一人暮らし老人を対象にした副食サービスや誕生祝い、理髪奉仕、障害者対象の外出送迎介助も。一人暮らし老人の家に二日以上、新聞や牛乳がたまっている場合、配達員が同委員会に連絡する態勢もとられている。
「○○さんが寝たきりになった」との情報があれば、情報センターが十三項目の「福祉調査異動届」を民生委員から提出してもらい、推進委員におろしてボランティア活動に入る。
けががもとで寝たきりになっている同町愛本新の石本あいさん(八四)は、月二回の「入浴ふとん乾燥車」と年四回の医師訪問を受けている。ふろはベッドのすぐ横で入れるので大助かり。「入浴はいい気持ちで待ちどおしい」という。
「おらはうす宇奈月」の施設ボランティア活動も盛んだ。昨年九月から始めたもので、町ボランティア友の会や町老人クラブ連合会など、登録人数は五百九十六人。草むしりやシーツ交換、俳句指導、買い物介助、清掃などさまざま。
なかでも宇奈月中は、部活動の一環としてボランティアに取り組んでいる。今年度事業として生徒会が決めた。テニス部や野球部などの生徒が六月から十月まで計十回、施設の窓ふきや草刈り、お年寄りたちの話し相手などをし、喜ばれている。
同協議会の奥田利則会長は「ボランティアを受けた人からの『ありがとう』といいう喜びの声が、私たちへの報酬だ」という。
こうした活動について入善町社会福祉協議会の板倉淳子主任(五二)は、「通常は行政が持っている個人情報を、宇奈月では社会福祉協議会が持っている。プライバシーの問題があって複雑だが、それが正しい姿だと思う」と話している。
白黒写真(省略)
特別養護老人ホーム「おはらうす宇奈月」で、ボランティア活動する宇奈月中学校の生徒たち=宇奈月町下立で
1995年(平成7年)6月23日(金)KNBTV 18:30〜 富山県内放送
ニュースプラス1
ボランティア情報
1995年(平成7年)6月2日(金)KNBラジオ 富山県内放送
災害時における打ち合わせ会
1995年(平成7年)4月27日(木)讀賣新聞 富山県版
焦点
阪神大震災きょうで100日
ボランティア、今後は?
「奉仕」超え自然に
企業など理解不可欠
阪神大震災の発生からきょう二十七日で百日−。多くの人命と資産を奪ったこの災害は、地震とは無縁と言われてきた本県にも防災対策の見直しを根底から迫っている。また、自然災害に対する、”無力感”を乗り越える動きとして、ボランティアの存在が際立った。「困っている人たちのために、何かできればと思って」。本県からも個人あるいはグループで、数多くの救援ボランティアが現地入りし、小回りの利かない行政に代わって、住民の多彩なニーズにきめ細かく対応した。「復興の立役者だった」(原秀樹・神戸市民福祉人材センター所長)という評価も。本県や近隣の県で、このような大災害が起きた場合、ボランティアはどこまで有効なのだろうか。百日という節目を機に、ボランティアの現状と可能性を探った。(山口 正雄)
県ボランティアセンター(橋本彰所長)は、さる二月上旬から三月下旬にかけて救援ボランティア延べ八十五人を被災地に送りこんだ。参加者は、会社員や公務員、学生などさまざま。
富山市鵯島、銀行員西村康浩さん(三二)は、第二陣(二月上旬)と、第九陣(三月中旬)の二回、現地入りした。「奉仕の意識はなかった。同じ日本人が困っているのを、傍観していることができなかった」と、動機を語る。
特定の人たちが特定の人たちのために”奉仕”する、そんなとらえ方をされてきたボランティアの意味を根底から問い直す出来事でもあった。
自ら現地入りしてボランティア活動をした宇奈月町社会福祉協議会の事務局長、本波隆さん(四四)は、こうした参加者の熱意について「自分に何ができるかを、それぞれが考えて、直ちに行動を起こした意義は大きい。ボランティア=奉仕という既成のイメージからからも大きく踏み出した」と分析、震災でボランティアに対する市民の意識が変わりつつあると見る。
一方で、ボランティアが置かれた現状と限界も浮き彫りになった。
富山市太郎丸の医師堀文さん(三五)は二月上旬、週末の休暇を利用して、救援ボランティアとして現地入りし、避難所での配給や施設の介護作業にあたった。
「体の不調を訴える人が多くいたが、スタッフや医療用品が乏しく応急処置しかできなかった。個人として参加しても、参加者の本職が十分生かせるようにしてほしい」と、ボランティアセンター間の情報ネットワーク作りを求める。
企業の、ボランティアに対する理解の低さも露呈された。県内で、ボランティア休暇制度を導入している事業所は十六(一九九四年度)。このうち七日以上の休暇を認めているのは北陸電力、第一交易、三菱レイヨンの三事業所のみ。
他は、一、二日が十事業所。三−六日が三事業所。導入している会社でも、幹部社員が休暇制度の存在を知らないケースが多々あることが、取材の中で分かった。県の救援ボランティアに参加した会社員の多くは、有給休暇を使った。
「する方もされる方も初めて」という声が聞かれた今回のボランティア。今、地域ボランティアの重要性を見直す動きも出ている。
富山市社会福祉協議会には、八十四の団体、二千八百三十二人がボランティアに登録されている。週や月単位での活動だが、一人暮らし老人宅への給食サービスや介護サービス、視覚障害者のための朗読サービスなど、日常生活に深く入りこんでいるものも多い。
地球環境科学が専門で、昨年四月から「ボランティア概論」を開講した富山大の宇井啓高教授は、「ボランティアを特別視しないで自然に受け入れるような意識改革が今後ますます重要。そのためにも地域のボランティアを盛んにして欲しい」と強調する。
既存の組織充実がカギ
震災後、直ちに有志による「小矢部市民の会」を結成、炊き出しなどの活動を行った小矢部市の会社社長、辻義夫さん(四五)は「テントの設営の仕方や、コンロやなべといった装備品の用意に至るまで、個人で出来る活動には限界があると痛感した。既存のボランティア組織を核にした活動の充実が求められている」と、反省点を挙げる。
百日を振り返って、辻さんは一層その思いを強くしている。
確かに、ボランティアの”頑張り”が盛んに取り上げられた。だが、辻さんは、「(震災は)ボランティア組織の脆弱な基盤を露呈させた」とも言う。各組織間の連携不足による情報の混乱などで、本来発揮できるはずの力の何分の一しか生かせなかったからだ。
いま、こうした教訓に立って、現地でボランティア活動をした人たちと、地域ボランティア組織との連携強化の模索も始まった。
西村さんは「富山などで阪神大震災並の災害が起こった時、どのような行動がとれるのかなど、協議を重ねている」という。
手助けを必要とする”弱者”がどこにいるのか−。他の地区から駆け付けた者には、にわかにはその辺の事情が分からない。「もっとも良く、地震のことを知っている人なり組織が、救援の核となるべきだ。そういう体制作りを進めることが、いざという時に、威力を発揮できるはず」と、辻さん。
いま、(自発的ボランティア)は最初の一歩を踏み出したばかり。うまく根づくかどうかは、この大震災の記憶をどこまで生々しく伝えていくかということとも深くかかわっている。
「疎開」今は半分以下に
県教委によると、阪神大震災で被災し、県内で疎開している児童・生徒は、新学期が始まった直後の十四日現在、小学生十九人、中学生六人、高校生四人の計二十九人。
ピーク時のさる二月二日には、幼稚園児一人を含む七十六人を県内の学校で受け入れていた。震災の復興に合わせて、住宅の修復などで自宅へ戻るケースが増え、現在はピーク時の半分以下になっている。
震災留学児童を受け入れている学校の校長、教頭らによると、児童らはおおむね明るく活発に、勉強や運動に励んでいるという。
カラー写真(省略)
被災者の声をくみ取るためにもボランティア組織の連携が必要(2月13日、神戸市灘区)
1995年(平成7年)2月28日(金)朝日新聞 富山県版
ボランティアの重要性痛感
物資の運搬や後片付け
体験も生々しく
阪神大震災の集い 宇奈月
宇奈月町ボランティアセンターと同町社会福祉協議会が共催した「阪神大震災ボランティア現地報告」の集いがこのほど、同町の中央公民館であった。同協議会の本波隆事務局長が五日から八日まで神戸市で体験したボランティア活動を紹介。災害時におけるボランティアの重要性を訴えた。
本波さんは、兵庫県と神戸市、富山県、宇奈月町の人口や面積、市区町村の数、阪神大震災の犠牲者と負傷者数、火災件数、避難者数を示し、今回の被害がいかに大きかったかを明らかにした。
被災地のスライドを上映しながら、同市中央区のこうべ市民福祉交流センターでの物資運搬や東遊園地公園での救援物資についても報告。この中で、八十五人の若者ボランティアの活躍ぶりのほか、物資には様々な種類があって、分けるのに手間取ったことなどを話した。
同市灘区の八十歳の母親と身体障害者の息子(五六)が暮らす被災者宅では、散乱した部屋の後片付けや給水車からの水の運搬などを手伝ったという。「延々と続く倒壊した家並みや、へこたれずに頑張っている市民の姿を見て、涙が止まらなかった」とのべ、約八十人の参加者を感動させた。
白黒写真(省略)
ボランティア活動を報告する宇奈月町社会福祉協議会の本波隆事務局長=同町の中央公民館で
1995年(平成7年)2月24日(金)讀賣新聞 富山県版
被災地の惨状を報告
ボランティア隊員が講演
宇奈月
宇奈月町社会福祉協議会(奥田利則会長)は二十三日、阪神大震災の被災地でボランティアとして活動した同会の本波隆事務局長による報告会を、同町中央公民館で開いた。約八十人が出席した。
本波事務局長は今月五日から八日まで、神戸市中央区と灘区で救援物資の仕分け作業や、被害を受けた市営住宅の片付け作業などに従事した。
報告会ではまず、倒壊した建物やボランティア活動の様子を、本波事務局長が自ら撮影したスライドで紹介。
また、救援物資の仕分けでは、食料や衣類などの品物が雑多に入り交じり作業に手間取ったこと、神戸市職員の不眠不休の奮闘ぶりや被災地の人々の様子を語り、支援の必要性を訴えた。
本波事務局長は「本当に同じ日本で起きたと信じられないくらいだった」と話していた。約八十人の参加者はメモをとるなどして熱心に聴き入っていた。
白黒写真(省略)
活動報告をする本波事務局長
1995年(平成7年)2月24日(金)北日本新聞 富山県版
助け合いの大切さ痛感
被災地派遣のボランティア
現状と活動を報告
宇奈月
宇奈月町ボランティア研修会が二十三日、町中央公民館で開かれ、阪神大震災の被災地で支援ボランティアとして活動した、本波隆町社会福祉協議会事務局長が現地報告した。
同町社協は震災後、町民に現地ボランティアを募っており、これまで本波事務局長ら二人が被災地へ派遣された。現地報告は、被災状況の認識を深めてもらいボランティアへの協力を求めることと、ふだんからの地域の助け合いの重要さを認識してもらおうと行った。
本波事務局長は今月初旬、県ボランティアセンターの災害救援部隊に参加。報告は、最初に、死者が宇奈月町の総人口の八割に当たり、六十歳以上の犠牲者が半数を占めていることなど、同町や富山県の数値と比較して紹介。被災地で撮ったスライド上映して、被災の大きさを知ってもらった。
活動内容については、初日は神戸市中央区の東遊園地公園で救援物資約六十トンの搬入や仕分け、配布を手伝い、二日目は障害者宅(灘区)に出掛け、家の中の片付けや給水車からの水運びを手伝ったと説明。
本波事務局長は、ボランティアを通して「人の心の温かさを実感した」と語るとともに、日ごろの助け合いの心の大切さを訴え、参加者は熱心に聴き入った。
白黒写真(省略)
阪神大震災のボランティア現地報告をする本波事務局長
1995年(平成7年)2月22日(水)北日本新聞 富山県版
学ぼう
▽阪神大震災救援ボランティア報告会
宇奈月町ボランティアセンターが二十三日午後一時半から、同町中央公民館で開く。
同町社会福祉協議会の本波隆事務局長が、現地での体験を発表する。
問い合わせは同センター、電話0765(62)1006
1995年(平成7年)2月19日(日)讀賣新聞 富山県版
阪神大震災から1か月
富山は何を学んだか
ボランティア
貴重な多くの現場体験
優れたリーダーも不可欠
神戸市中央区の神戸市民福祉交流センター。十三日夜、富山県ボランティアセンター(橋本彰所長)が送り出した十四人のボランティアが寝泊まりする大部屋のホワイトボードに、翌日の仕事を知らせる七枚の紙が張り出された。
荷物の仕分けなどが多かった震災直後に比べ、最近は、各家庭からの個別の要望にこたえる仕事が増えてきた。この日も、「家の壁の補修」「目の不自由な女性の入浴介護」などが掲げられた。
小矢部市の南昭仁さんは、神戸市長田区の被災者から依頼があった「家の壁の補修」を選んだ。一緒に行ったのは、静岡県から参加した土建業者。崩れ落ちた台所わきの壁に、外側から手際良くベニヤ板を打ちつけていく。たまたまこの静岡県からの参加者がいたために、仕事は短時間できれいに片づいた。
入浴介護にしても、その経験を持ったボランティアなら、より行き届いた援助ができる。どのような経験や資格を持ったボランティアが集まっているのかを把握しておくことが、質の高い支援活動につながる。
小矢部市の松原潤さんは、「小矢部市民の会」(辻義夫代表)のメンバーとして、震災六日目から約三週間にわたって、神戸市東灘区の県立御影高で炊き出しなどを行った。
最初はすべてメンバーたちが煮炊きをしたが、震災から半月もすると、被災者自身が炊事当番を受け持つようになった。「ボランティアはいつまでも居る訳ではない。被災者の生活を助けるボランティアから、自立を促すボランティアに変わっていくことが必要だ」と松原さんは考える。
御影高とは違い、今でも炊き出しボランティアに頼りきっている避難所もある。被災地の復興を本気で助けようとするなら、引き際を考えておくのもボランティアの責任かも知れない。
松原さんは、九一年の石川国体で、身障者スポーツ大会のボランティアを経験している。「あのときの行政主導のボランティア活動は、やるべきことが決まっていた。今回は違う。何ができるかを自分で考えなければならな」という。
橋本所長も、「余暇の有効利用などを考えているボランティアと、災害時のボランティアは別物だと分かった。県内でボランティア登録している約一万五千人のうちどれだけが、災害時に頼りになるだろうか」と心配だ。
今、自分が何をすればよいか、何をしなければならないか−。それを自己の責任で決めていく、文字通りの自発性こそが、被害地に問われている。
やはり神戸市でボランティア活動してきた宇奈月町社会福祉協議会の本波隆事務局長は、「指揮系統に携わる人が少ない」と感じた。働きたくてうずうずしている若者が、指示を出すとワッと仕事に取りかかるのだ。自ら進んで仕事を見つけるのが災害時の基本だが、現実には優れた指揮者が欠かせないようだ。
温かい食事を出し、仮設トイレに電灯をつけ、お年寄りの水くみを手伝って、被災者を元気づけてきたのは、まぎれもなくボランティアの存在だ。
ボランティアは、今回の大震災の現場でどう動いたのか。被災地に入ったボランティアから、できるだけ多くの体験談を聞いて、本県が被災地になったとき、どのような手順で自立していくのかを、具体的にシミュレーションしてみることが、ぜひとも必要だろう。(おわり)
保坂 直紀
白黒写真(省略)
崩れた壁を修復する南さん(左)らボランティア
1995年(平成7年)2月10日(金)富山新聞 富山県版
卒業前に「役立ちたい」
阪神大震災ボランティア
高校生の応募相次ぐ
高岡一の松倉さんら「自分の目で現地を」
阪神大震災ボランティアなどの募集に、卒業を控えた高校生の応募が相次いでいる。県ボランティアセンターが十二日に派遣するメンバーの中にも、高岡一高三年の松倉さやかさん(一八)=富山市布目南町=ら今春卒業を控えた女子高生三人が名乗りを上げており、「自分で役に立つことなら、何でもします」と目を輝かせている。
同センターによると、大震災の発生一週間後から県内各市町村のボランティアセンターと連携を取り、現地派遣のメンバーを募集したところ、これまでに百件程度の応募があり、卒業を控えた高校生からも十件を超える問い合わせがあった。
今回現地に向かう十四人の中にも、松倉さんと富山商高三年の島崎三奈さん(一八)−富山市水橋山王町−、新湊高三年の尚和厚子さん(一八)−新湊市宮袋−が名を連ねており、五日に派遣した第二陣にも、富山市と入善町から高校三年生が一人ずつ加わっていた。
富山市舟橋南町の県社会福祉会館で研修会が開かれた九日、尚和さんは登校の日と重なって欠席したが、参加したほかの二人は第二陣のメンバーの一人、宇奈月町社会福祉協議会事務局長の本波隆さん(四四)から現地の様子などを聞き、決意を新たにした。
三人はそれぞれ県外の大学への入学が決まっているが、これまでにも、同センターを通して高齢者福祉施設訪問などのボランティア経験が豊富で、松倉さんが「体力だけには自信がある」と話すと、島崎さんも「テレビだけでなく、自分の目で現地を見て焼き付け、実際に役立ちたい」と、それぞれ決意を込めた。
白黒写真(省略)
「自分たちにできることなら」と励まし合う島崎さん(左)と松倉さん=富山市の県社会福祉会館
1995年(平成7年)2月10日(金)毎日新聞 富山県版
災害ボランティアの
事前説明会を開催
第三陣の参加者
阪神大震災の災害救援ボランティア第三陣の事前説明会が九日、富山市舟橋南町の県社会福祉会館で開かれた。
今回は十八から五十六歳の十四人が参加し、十二日〜十八日の予定で、神戸市中央区の同市民福祉交流センターを中心に活動する。現地から前日帰ったばかりの本波隆・宇奈月町社会福祉協議会事務局長の話をもとに、準備するものや現地の様子などが説明された。
本波事務局長は「一軒や二軒だけでなく膨大な家が倒れているのを見て、言葉が出なくなった。実際に自分の目で見て、『自分がやらなきゃだれがやる。また行かなきゃ』という気持ちになった」と話した。また参加者最小年の島崎三奈さん(一八)は「現地はひどいと聞いている。自分の目で見てやれることをやりたい」と抱負を語った。
1995年(平成7年)2月9日(木)チューリップTV 18:30〜 富山県内放送
ニュース
阪神大震災ボランティア
本波 隆(ほんなみ たかし)